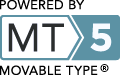最近読んだ本が「ピアニスト
この本のモデルになっているのが、あのユジャ・ワンと知り、とても興味が沸き手にしました。
エティエンヌ・バリリエというフランスの男性作家が書いた作品で、2人の(ヨーロッパ人)音楽評論家が中国人の女性ピアニスト(メイ・ジン)の演奏をめぐってネット(ブログとメールのやりとり)で激論を戦わせるという内容です。
登場する2人の評論家のうち、一人の年配の評論家は(著者曰く)理想主義者。
彼女の演奏を「奇跡」と評し、好意的に評価しています。
かたや若い評論家は、懐疑的な考えを持っており、東洋のピアニストが、ヨーロッパ人のように(クラシック)音楽を理解することはできないし、理解しようともしていない、と言い切ります。
2人の争点は、ヨーロッパのクラシック音楽が普遍的な価値を持っているか否かということ。
彼らのやりとりの文章はかなり哲学的で譬喩も多く、(正直)クラシック音楽に造詣が深くないと読み進むのは困難な気がしました。
裏をかえせば、古今のピアニストや作曲家についてある程度知識や教養のある人には、知的興味の尽きない本と言えるかもしれません。
原題は「Piano chinois - Duel autor d'un recital」 (Etienne Barilier)
(直訳すれば中国人ピアニストでしょうか。)
そもそも、バリリエがこの本を著すきっかけとなったのは、
中国、韓国、日本といった(極東の)国々でヨーロッパのクラシック音楽がごく自然に、ありのままの姿で愛好されていることを知り、驚嘆(感動)したことが動機になっています。
巻末に、著者が日本で行った講演会での言葉が掲載されているのですが、アニメ『のだめカンタービレ』、村上春樹の『スプートニクの恋人』、小川洋子の『やさしい訴え』などの作品から、強烈なインスパイアを受けたと述べています。
もしかしたら、そもそもの発祥のヨーロッパ以上にヨーロッパのクラシック音楽が生活や日常に存在している...
そういう危惧をも感じたのかもしれません。
私たち(日本人)にはない発想ですが。
彼は、ユジャ・ワンの演奏をスイスとフランスで2度聴いているそうで、
その時見聴きした体験を描写していると思われる箇所が随所にあり、
(実際に私も2度演奏会を聴いたことがあるので)読み物としても楽しめました。
ストラヴィンスキーのペトリューシュカを演奏している時の表情について、こんな表現を用いています。
以下引用
『テクニックの困難さを克服して、この若いピアニストがどうやってあのような力を抜いた顔つきを保ち、落ち着いて唇を半開きにしたまま演奏できるのか不思議だ。かの熟練のワイセンベルグでされ、この曲を弾く時は真剣でとげとげしい様子を見せたものだ。まさに「奮闘努力せよ」だ!メイ・ジンの方は、むしろ「笑う門には福来る!」か。』
登場する老評論家=バリリエ自身?と思わせます。
また、演奏曲(スカルラッティ ソナタK87、ショパンのピアノソナタ第2番「葬送」)についての分析も面白い。
バリリエ自身が音楽関連の著作や受賞を受けていることからも、かなりクラシックについて勉強していることが窺われます。
話しをもとに戻しますが...
この本は、クラシック音楽がなぜこれほどまでに私たちに浸透しているのか?ということについて、あらためて考えるきっかけをもらった気がします。
日本の古典音楽を口ずさむことはできなくても、ショパンの子犬のワルツを聴いたことの無い日本人はおそらく一人もいないでしょう。
そういう意味では、全てではないにせよクラシックはすでに普遍的な価値を得ているのではないか。
また、近代のピアニストは、偉大な作曲家たちの忠実な表現者から、創造者にTransformしてきているのではないか?とさえ思うのです。